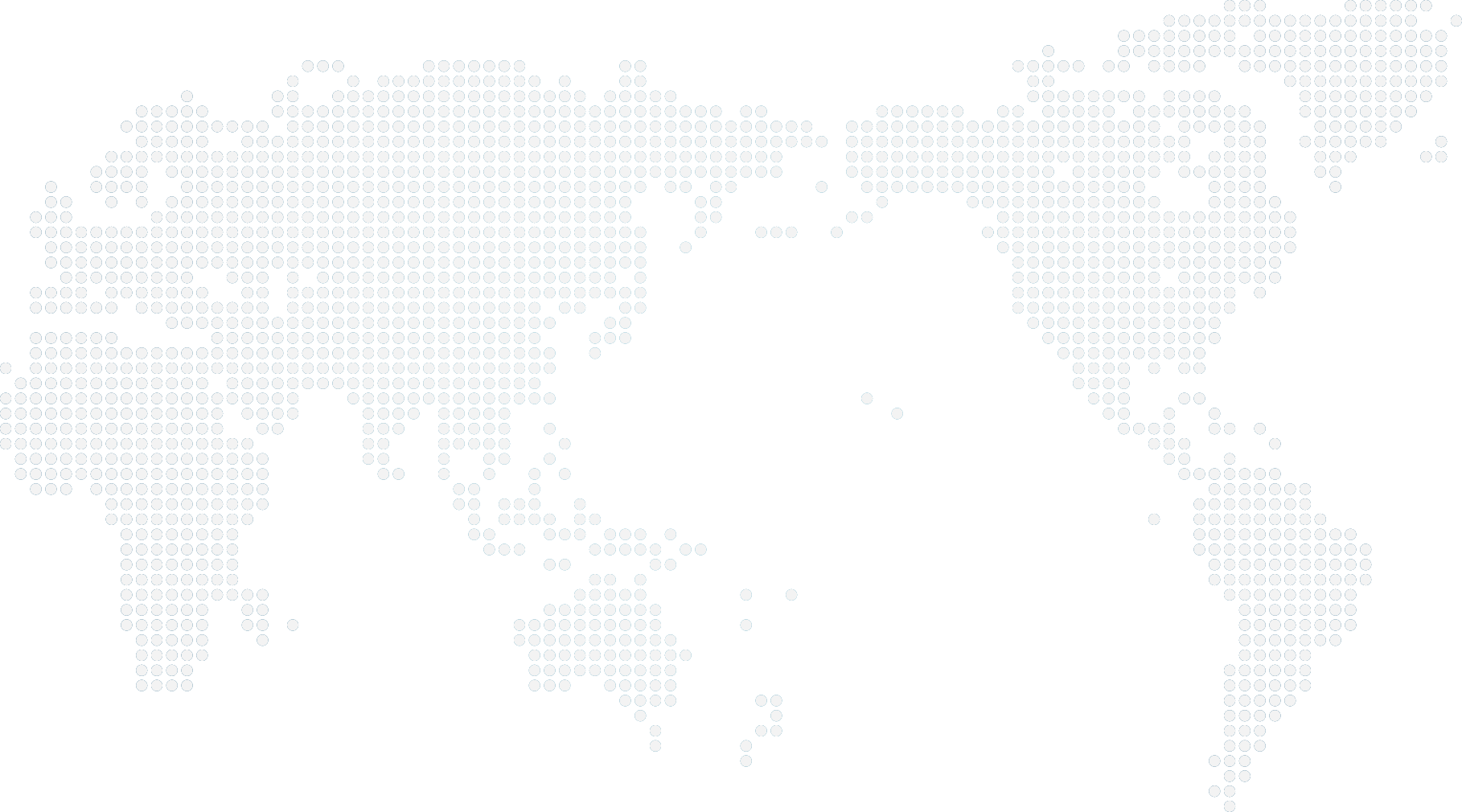SDGsに関連する主な用語を紹介しています。
みなさんはいくつ知っていますか?ぜひ、辞書代わりにご活用ください。
「し」の用語一覧
食品廃棄
可食部外のもの、腐敗、食べ残し、売れ残りなどの原因により廃棄されてしまう食品の総称。食品廃棄物に分類される魚や肉の骨、野菜の種や芯などと食品ロスに相当するまだ食べられる料理や食材の食べ残しの2分類。世界では飢餓や栄養不足人口がいる一方先進国を中心に食品廃棄がある不均衡状態や焼却による環境汚染、経済損失が問題となっている。
CDP
環境問題に取り組むのNPO団体CDP(Carbon Disclosure Project)のこと。機関投資家、企業、自治体、政府が環境への影響を管理・把握するための世界で唯一標準化された国際開示システムプロジェクトである。環境課題に行動するため「開示、洞察、行動」の3システムを持つ。グローバル社会が環境影響を正しく把握し持続可能な発展を目指す目的の元運営されている。
森林率
国土や地域別などにおける面積に対し森林が占める割合。世界平均が30%台に対し日本は67%。木材の適切管理や保護の法整備が整っていることから高い数字を誇る。世界では毎年520万ヘクタール減少しており生物多様性、森に依存する人々の人権侵害、気候変動進行などの危険性が高まっている。森林減少の要因となる開発を持続可能に転換する必要性がある。
ジェンダーバイアス
男女の性別に基づいた役割に対する固定概念。社会生活における役割分担、ワード、色や形などが具体例として挙げられる。日本では特に政治・経済分野で課題が大きい。賃金格差、教育格差、LGBTQ+の差別や偏見の解決には欠かせないもの。
循環型農業
従来の工業型農業のように農薬や化学肥料頼みではなく、肥料として廃棄物も併用して活用することで環境負荷を減らすことを目的とした次世代型の農業体系。 自然に近い形で土壌の生物多様性を守りながら生産性の両立を目的としており、持続可能な農業の観点から取り組みが進められている。
障害者雇用
「障害者雇用促進法」により国が定めた障がい者に関する雇用のこと。企業で雇用する従業員の内2.3%に対し義務付けられている。「身体障害者手帳」を保有する身体障害者、「療育手帳」を保有する知的障害者、「精神障害者保健福祉手帳」を持ち就労可能な状態だと判断される精神障害者が対象となる。
関連記事:「障害者雇用とは|企業義務や法律、助成金、相談先まで解説」
消費支出
消費の内生活費や家計費に分類されるもの。日常生活を営む上で必要な消費やサービス購入にかかる現金・カード。商品券などを用いた支出が主となる。具体的な項目は食糧費、住居費、医療費など。仕送り金や贈与金、消費税や自動車取得税なども含まれる。
省エネ
石油や石炭、天然ガスなど限りある資源を効率よく使用すること。日本はエネルギーの国内自給率が低いことによる安定供給確保の目的や、近年では地球温暖化など環境対策の側面から重要視されている。 家庭内における省エネの他、工場に対しては省エネ法が定められている。
人工光合成
植物の光合成の仕組みになぞらえて、太陽エネルギーを利用した変換技術。具体的には太陽光、CO2、水を原材料とし光触媒を利用して化学品を合成するもの。エネルギー問題の解決に有力な方法として注目されるが、現状太陽光からエネルギーへ変換される割合が低いことや、燃料などの有機化合物を人工的に生産することなどの課題もある。
食料自給率
国ごとに消費している食料のうち、国内で自給される割合を示したもの。食料と農業の動向を把握する指標としても用いられる。主流はカロリーベース総合食料自給率のことを指す。計算式は1人が1日に消費する国産食品のカロリー÷1人が1日に消費する全食品のカロリーで求められる。他には各品目の自給率を重量ベースで算出した品目別自給率などがある。
女性推進法
従業員数が301人を超える企業に対し、働くことを希望する女性が自身の個性や能力を発揮され活躍できる職場環境を整備することを目的とし2015年に制定された。
3つの基本原則からなり、企業は数値目標や取り組み内容を盛り込んだ行動計画の策定・提出の他女性活躍状況の情報公開が求められる。2022年4月からは101人以上の企業まで対象範囲が拡大した。
シェアリングエコノミー
共有経済とも呼ばれ、企業や個人がモノやスキル、空きスペースなどを必要とする人に提供・共有するサービスや経済形態。様々な資産の活用を通して多様なニーズの選択、レジリエントかつ循環型社会へ寄与するもの。